つくばのKEKでは、素粒子ニュートリノを加速器で人工的につくり、250km離れた岐阜県・神岡にあるスーパーカミオカンデ検出器に打ち込む「K2K」と呼ばれる実験が行われていました。
「KEK to Kamioka」を意味するK2Kは、現在の最先端のニュートリノ研究の礎になった実験です。今回の一般公開では、役目を終えた「前置検出器」と呼ばれる装置の遺構を公開します。特別企画として、光と音楽による空間演出も行います。

1999年3月に始まり、2005年1月までに終了したK2Kは、「ニュートリノ振動」と呼ばれる現象を観測する実験でした。

ニュートリノ振動はニュートリノに質量があると起きます。スーパーカミオカンデでの大気ニュートリノの観測で見つかり、梶田隆章博士が2015年にノーベル物理学賞を受賞していますが、K2Kでは2004年に人工ニュートリノでもやはり起きていることを確認したのです。
それらの成果につながったK2K実験の「前置検出器」は、深さ16mの大きな穴に設置されています。地上階から見下ろすと銀色の巨大な円筒形の構造物に見えます。「1キロトン水チェレンコフ検出器(1KT)」と呼ばれます。
構造はスーパーカミオカンデと基本的に同じです。直径10.8m、高さ10.8mもあるタンクの中に超純水を満たし、ニュートリノが水中で稀に反応する際に発生する微弱なチェレンコフ光を高感度の光電子増倍管680本でとらえます。できたばかりのニュートリノのエネルギーなどを観測し、250km先のスーパーカミオカンデでの観測データを比較することで、実験を支えました。
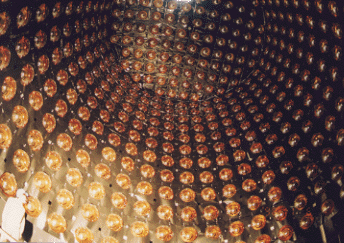
1KTが設置してある深さ16mの穴の手前には、1KTを保管する役割のもう一つの前置検出器もありましたが、現在は撤去されています。
今回の一般公開では、その空きスペースを利用して、光と音楽による空間演出を行います。
昨年のKEK一般公開で「コッククロフト・ウォルトン型加速器」をライトアップし、KEK50周年パフォーマンス映像の演出を再現した多摩美術大学の森脇裕之教授がプロデュースする約10分間のプログラムで、10時0分、11時0分、12時0分、13時0分、14時0分、15時0分の6回上演します。映像は岡本晃樹さん、音楽は書上奈朋子さん、照明は森脇教授が担当します。
空間演出をしていない時間帯も見学は可能です。ニュートリノ研究のパネル展示も行います。K2Kの後継に当たり、現在継続中のT2K(Tokai to Kamioka)実験のこともわかります。
なお前置検出器が置かれている建物は深さ16mの穴があり、容積が5000立方メートルあるため、空調機は本来、20台必要です。しかし換気をうまく制御することで1台だけで除湿効果を実証する実験も行っています。
そのおかげで建物内でも快適に過ごすことができます。今回の見学では、その実証実験の効果も感じてください。
一般公開での前置検出器公開は20年ぶりです。構内バスの5番のりばで降り、案内に従って歩いてください。
